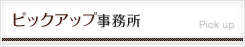遺言の自由の限界
被相続人は、生前に自己の財産を自由に処分することが出来ますし、遺言で遺産の分け方を自由に指定することも出来ます。
しかし、一定の範囲の相続人については、遺産が分け与えられることにある程度の期待を抱くこともあって当然です。
例えば、被相続人である女性に子供が1人いて、夫が死んでしまっているケースで、亡くなる1年前に知り合った男性を好きになり、全財産をその男性に贈る(遺贈する)という遺言を書いて死亡したとしましょう。
子供にとっては、遺言がなければ、遺産を全て1人で相続することが出来たはずなのに、その遺言の存在によって、全く権利がなくなることになるでしょうか。
亡くなったお母さんが自分で築いた財産なら、ご本人の遺志を尊重したいということにもなるでしょうが、相続発生時は、お母さん名義の土地、建物であっても、元々はお父さんがその父親から引き継いだ土地・建物で、現在自分もその家に住んでいるとなると、遺言一つでそれが他人の所有になるというのも、気の毒です。
そこで、民法では、兄弟姉妹を除く相続人には、遺産の一定割合を確保することが出来るようにしました。
その確保できる割合を遺留分と言います。
遺留分の割合
遺留分は、直系尊属のみが相続人である時は、遺産の全体の3分の1で、それ以外の場合、例えば、配偶者がいる場合や子や孫がいる場合には2分の1と決められています(民法1028条)。
相続人が複数いる場合には、遺留分の全体の割合をさらに法定相続分に従って分けることによって各相続人の遺留分が定まります。
前述の子供1人が相続人のケースでは、その人の遺留分は2分の1です。
夫1人、子供2人が相続人というケースでは、夫の遺留分が4分の1、子供はそれぞれ8分の1ずつとなります。
遺留分の減殺請求
遺言や生前贈与の内容が、各相続人の遺留分を侵害するものであっても、遺言や生前贈与自体は無効になるわけではありません。
遺留分を侵害されたことに不満がある場合、遺留分のある相続人(遺留分権利者)が、贈与や遺贈によって侵害された遺留分を取り戻せるよう求めることが出来ることとなっています。
これを減殺請求と言います(民法1031条)。
減殺請求権は、相続の開始と減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年を経過すると時効で消滅します。
贈与・遺贈があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過するとやはり時効となります(民法1042条)。
遺留分の算定の基礎
遺留分の算定の基礎となる相続財産は、亡くなった日に有していた財産だけでなく、贈与した財産の価額を加え、債務を控除して算定されます(民法1029条)。
相続開始前の1年間に行った贈与の価額は全て加算され、また、1年以上前の贈与であっても、被相続人と受け取る相手方の双方が遺留分を侵害することを知って贈与した価額も、遺留分を算定する基礎の財産となります(1030条)。
例えば、父親が亡くなる半年前に5000万円の預金を長男に贈与したため、死亡時には1000万円しか預金がなかったという場合には、死亡時の1000万円に贈与額5000万円を加え、6000万円についての2分の1、つまり3000万円が遺留分となります。
相続人が長男・次男だけであれば、次男は1500万円の遺留分がありますので、1500万円に達するまで遺留分減殺請求をすることが出来ます。
また、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本としての贈与を受けている場合は、遺産の前渡しと考え、1年前という時期を問わず遺留分の算定の基礎に加えて取り扱われます。