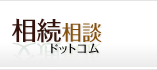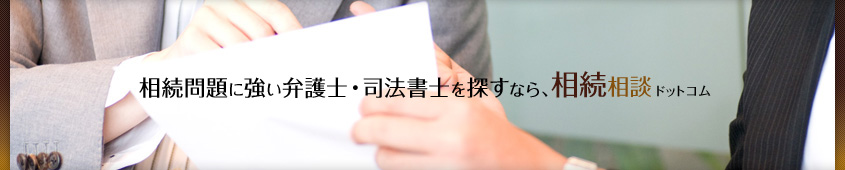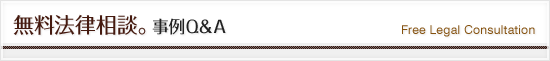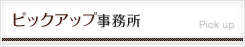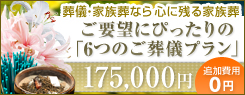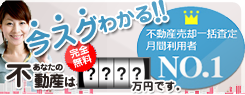兄の建てた家に両親と同居していました。両親亡き後私達にそこに住む権利は?
4人兄弟で弟が1人結婚して家を出ています。
ニ十年前、兄が私と両親で住んでいた家を父が渋るのを押し切り、住んでいた家を壊して二世帯住宅を建て、兄の一家と同居を始めました。
家のローンと税金は兄が、水道光熱費は父が払う事になりましたが父が病気で亡くなり、その後母も病気で寝たきりになり亡くなりました。
両親の入院も介護費用も私のお金と両親の年金でまかない、介護は私と同居の弟でしていました。
その間も今も水道光熱費はうちで払っています。(兄一家の使い方が激しく毎月6万前後かかります)
母が生前やはり水道光熱費の支払い等に困ってカードで借りた借金も私が払っています。
兄は家も土地も自分と子供のものだと思っており、私達は居候なので二世帯分の水道光熱費を払うのは当たり前だと思っているようです。
介護で仕事を減らしてしまったのですが年齢的に転職も難しく体も壊してしまい病院にも通っており、借金をして水道光熱費を払っていますが、限界です。
家を出たくてもその費用さえありません。
私や弟にはなんの権利もないのでしょうか?
-
- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
家なり土地の名義がどうなっているかが問題です。父の共有名義であれば相続権があるので兄個人だけのものとはいえないでしょう。又家が兄個人名義であっても底地が父名義であれば底地は相続する権利があるので、底地の共有権を無視することは出来ないでしょう。又底地も兄単独名義だとしても土地は父から特別贈与を受けたことになりますからそこらへんの事情を考慮すれば兄は自分だけ物だとは言えないでしょう。ここに住み続けて家を支えてきたということで居住権はあるといえます。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
-
- おがわ町総合法務事務所
達脇 清将
住む権利を主張することは不可能ではありません。水道光熱費は、ご自分が居住している範囲内でのみ支払えば十分です。諸々の債務は司法書士等専門家に依頼して解決できます。
こんにちは。埼玉県比企郡小川町で司法書士をしている者です。
全体的に、諸々細かいお話をうかがわないと確答はできないのですが、
投稿しておられる内容から、「通常想定される範囲内で」お答えします。
まず、家の(登記上)所有者名義がお兄さんで、そこに長年ご両親及び貴殿が居住している場合、
法的には、黙示の使用貸借契約が締結されていたと解釈できる余地があります。
当該使用の目的は「居住」ですので、その目的が達せられるまで、
つまり、ずっと住むことができる、ということにできる可能性があります。
次に、水道光熱費についてですが、貴殿が居住している範囲内(例えば半額)で、
貴殿には支払う義務がありますが、その余については、支払う義務がありません。
つまり、現状、払い過ぎ、ということになりますが、
これは、当事者間における黙示の取決めがあったとも言えますので、
過去にさかのぼって、払いすぎている分をお兄さんに請求することは難しいでしょう。
次に、ご両親の介護費用についてですが、これは、貴殿が子である以上、
特別な寄与があったとはほぼ認められません。
お兄さんに兄弟の人数で按分した額の請求できる余地がある、という程度です。
しかしそれも、貴殿がご自身の財産から出捐した額であり、
当然のことながら、ご両親の財産からの拠出分は控除されます。
最後に、お母様と貴殿の借金の件ですが、
その支払いに窮しておられる場合は、
司法書士か弁護士のいずれかに(いずれかしか処理できません)ご依頼されることを
強くお勧めします。
司法書士か弁護士ならば、借金以外にも、上記のことにつき
対応してくれると思います。
支払いが厳しいのであれば、悩まず、勇気を出して事務所の門を叩くべきだと思います。
ここまで書いて、司法書士や弁護士に依頼する場合、
費用が心配、というお考えもあるかもしれませんが、
条件が満たせば低廉な価格で依頼できる制度がありまして、
その制度を利用するための機関と契約している
司法書士(私もそのうちの一人ですが・・・)や
弁護士(こちらはあまりいないかも、です)もいます。
まずは、気持ちをしっかり持ってくださいね。
- おがわ町総合法務事務所
-
- 南木法律事務所
南木 道雄
建物について賃貸借又は使用貸借が成立していると解する余地があります。そうすれば継続して居住できます。
土地と建物の名義は誰でしょうか。おそらく土地はお父様で建物はお兄様の名義ではないでしょうか。
とりあえず、それを前提にします。
土地につきましては、お母様やご兄弟が相続人ですから法定相続分の共有持ち分は保障されます。
建物についてはそういうわけにはいきませんが、本件においては、名義人のお兄様との間で賃貸借契約(賃料は水道光熱費相当額の負担支払い)又は使用貸借契約(無償で建物を使用できます)が成立している、と解する余地があると思います。無論、契約書等の正式な書面はないでしょうが、これまでの事情からしてそう言える余地があると思います。 - 南木法律事務所